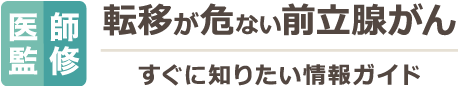食事の改善
このページの監修医師
医療法人健身会
周東寛 理事長
前立腺がんの転移は食事によっても予防対策が可能。こちらのページでは、その具体的な方法について紹介しています。
食事の注意点は生活習慣病予防と同じ?
前立腺がんは欧米に多く日本では比較的少ないがんですが、これには食生活の違いが関係していると考えられています。
肉類や乳製品を好む欧米型の食事が前立腺がんのリスクを高める可能性があるようで、厚生労働省と国立がん研究センターが行った大規模追跡調査でも、そのことを裏付ける結果が出ています。肉類や乳製品の過剰摂取を控えるという注意点は、生活習慣病の予防によく似ていますね。生活習慣病予防のために脂肪が多くこってりした食事を避けている男性も多いでしょう。
では、具体的にどのような食生活を意識すればよいのでしょうか?
まず乳製品ですが、前立腺がんのリスクを高める一方で大腸がんや骨粗鬆症、高血圧等を予防する効果も期待できるため、一概に避けるべきとは言えません。ポイントは低脂肪製品を選ぶこと。低脂肪ヨーグルトや低脂肪乳、チーズならカッテージチーズやパルミジャーノなど、飽和脂肪酸を避けながらもその他の栄養は補給できるものを選ぶとよいでしょう。
肉類も、たんぱく質が豊富な食材のため単純に食べなければいいというものではありません。脂身を残す、炒め物や揚げ物を避けるなど、なるべく脂肪の摂取を控えられる調理法・食べ方を心掛けましょう。
そのほか、がんに効くといわれている食べ物は色々あるので、その効果や根拠を調べた上で取り入れてみるのも良いかもしれません。くわしくはがんに効く食べ物とは?(外部サイト)で解説されているので、併せてチェックしてみてください。
「大豆」と「緑茶」を上手に取り入れよう
肉類や乳製品の過剰摂取を避けることが前立腺がんの予防に良いと分かりましたが、一方で、積極的に摂ることで前立腺がんのリスクを下げられる食品もあります。それが、大豆です。
前述した厚生労働省と国立がん研究センターによる大規模追跡調査で、大豆製品をたくさん食べることによって前立腺内に留まる限局がんのリスクが下がるという結果が出ているそう。具体的には、61歳以上で限局がんになるリスクは、豆腐や味噌汁などの摂取量が最も多い(1日107g以上)グループが、最も少ない(1日47g以下)グループの約半分。味噌汁単独でも、最も多い(1日2杯以上)グループは最も少ない(1日1杯未満)グループより35%低いとされています。
これは、大豆が含む「イソフラボン」が関わっていると考えられ、同調査ではイソフラボンの血中濃度が高いほど限局性前立腺がんのリスクが低くなるという結果も出ています。ただ、進行性前立腺がんとの相関関係は明らかになっていません。
進行性前立腺がんについては「緑茶」がリスクを下げると、同じ大規模追跡調査で示されています。1日1杯未満の緑茶を飲む人を基準に、1日1~2杯、3~4杯、5杯以上のグループに分けて前立腺がんのリスク変化を調査したところ、限局がんには変化が見られなかったものの進行がんのリスク低下した報告があります。1日5杯以上のグループでは、1日1杯未満のグループより約50%もリスクが減りました。どうやら緑茶に含まれるカテキンが、がん細胞の増殖を抑制する働きを持っていると考えられています。また、前立腺がんの危険因子のひとつである男性ホルモンのテストステロンを低下させたり、アンドロゲンの作用を抑えたりする働きも、前立腺がんのリスク低下につながると考えられています。
野菜や果物を含めたバランスの良い食事を!
ちなみに、生活習慣病予防のための食事法として「野菜や果物を積極的に食べましょう」とよく言われますが、これに関しては、前立腺がんのリスクとは関係がありません。野菜や果物の摂取が前立腺がんのリスクを抑えるという調査報告は、あまり見られません。
ただ、野菜や果物は、食道がんや胃がんといった他部位のがんや、循環器疾患などを防いでくれる効果が期待できます。厚労省と国立がん研究センターの研究班からも、「野菜は毎食、果物は毎日食べて、少なくとも1日400g摂ること」が推奨されています。
前立腺がんの転移・再発予防には、肉類や乳製品の過剰摂取に気を付けながら、緑茶を積極的に飲むよう心掛け、また野菜や果物などもバランスよく摂ることが大切になるといえるでしょう。
がん治療中でも栄養バランスの良い食事を摂るための工夫
がん治療中は抗がん剤の副作用で悪心や嘔吐、食欲低下がみられることも。そのため十分な食事が摂れなくなることもあり、体重減少や体力低下につながる可能性もあります。
以下に、「悪心・嘔吐」「食欲低下」「体重減少・体力低下」というそれぞれの悩みに対応する食事の工夫をまとめてみました。
悪心・嘔吐に対する食事の工夫ポイント
- 少しずつ回数を増やして食べる。盛り付けにボリュームがあると負担に感じるため器の数を増やして各盛り付けは少なくするのがおすすめ。
- 冷たくて口当たりが良く、飲み込みやすいものを食べる。
- 脂の多い食事は控える。煮る・焼くなどの調理法がおすすめ。
- 同じものを食べ続けると悪心の原因になるため、何種類かのメニューを交互に食べる。
- 嘔吐が多いときは脱水症状に注意。ミネラルや電解質の摂取を心掛ける。
- 匂いの強いものを避ける。
- 味付けをシンプルに。みりんや砂糖での味付けより塩味がおすすめ。
食欲低下に対する食事の工夫ポイント
- 自分の好きなものを、食べられるときに少量ずつ食べる。
- 好みの味付け・温度のものを食べる。
- 主食を変えてみる
- 汁物やスープなどを取り入れる
- お腹が空いているときは、時間に関係なく食べる。
体重減少・体力低下に対する食事の工夫ポイント
- 穀物やイモ類など主食を摂る
- 体力回復に必要不可欠な良質のたんぱく質を積極的に摂る
- 食欲増進に働きかける酸味や香辛料を取り入れる
動物性と植物性の油について
油には、動物性と植物性の2種類がありますが、マーガリンとバターなど一見すると判断できません。ただ、最近は植物性油が健康に良いと注目されています。どのような点が健康に良いのでしょうか。
植物性油は、n-6系(エヌ・マイナス・ロクケイ)脂肪酸やn-3系(エヌ・マイナス・サンケイ)脂肪酸と呼ばれる不飽和脂肪酸を多く含んでいます。n-6系脂肪酸やn-3系脂肪酸は体を作るうえでとても大事な成分なのですが、体の中で作ることができないため、自主的に摂取する必要があります。
n-6系脂肪酸とはいくつかの不飽和脂肪酸をまとめた名前ですが、その98%はリノール酸です。リノール酸は足りなくなると皮膚炎になることもある体にとって不可欠な成分。また、n-3系脂肪酸には、αリノレン酸やエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)などがあります。α-リノレン酸は植物油から摂取でき、EPAやDHAは魚介類から摂取できます。
このn-3系脂肪酸が非常に重要で、乳がんや大腸がん、肝がんなどのがんをはじめ、冠動脈疾患や脳卒中などの血管系疾患、加齢黄斑変性症や一部の認知障害、うつ病に糖尿病など多くの病状に対して予防効果の可能性が示唆されています。国内でも数多くの事例が報告されています。
動物性油には植物性油に比べて、飽和脂肪酸が多く含まれています。この飽和脂肪酸も重要なエネルギー源ですが、飽和脂肪酸をとりすぎると、血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が増えて動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが増加するとされています。
もちろん植物性油も摂り過ぎると肥満や、冠動脈性心疾患の原因にもなるそうなので、量には注意が必要です。同じ量であれば植物性油が健康に良いので、日々の料理に使う油を変えることで前立腺がんの再発予防や、健康維持に役立てるといいでしょう。
植物性油の種類
亜麻仁油
必須脂肪さんのαリノレン酸を多く含む油。
エゴマ油
αリノレン酸を多く含むが、オレイン酸が少ないため、酸化しやすい。
オリーブオイル
オレイン酸を多く含む油。
グレープシードオイル
必須脂肪酸のリノール酸が多く含まれている。
コーン油
コレステロールの吸収を抑える植物ステロールを含む油。
ココナッツオイル
ココナッツの白い部分が原料の油。
ごま油
必須脂肪酸のオレイン酸とリノール酸がほぼ同じ割合で含まれている油。
こめ油
米から作られる油。米ぬかにだけ含まれるγ-オリザノールが特徴の油。
大豆油
脂肪酸の組織の半分近くがリノール酸なことが特徴の油。
なたね油
オレイン酸の割合が高いので酸化しづらい特徴を持つ。
パーム油
酸化しにくい特徴があり、加工食品や惣菜のフライなどに使用されている。
ひまわり油
植物油の中でビタミンEがトップクラスの油。オレイン酸または、リノール酸が多いタイプがある。
べに花油
含まれている脂肪酸割合の8割近くがオレイン酸で非常に酸化しづらいのが特徴。
綿実油
ビタミンEが豊富で、必須脂肪酸のリノール酸とオレイン酸も含まれている。
落花生油
リノール酸とオレイン酸がバランスよく含まれている油。
緑茶はカテキンが有効ですが、過剰に取らない方がいいでしょう。 利尿作用があるため、細胞も合わせて脱水されてしまいます。
五大栄養素(糖、たんぱく、脂肪、ミネラル、ビタミン)が含まれている食材をバランス良く摂りましょう。
動物性の油は取りすぎると、血液の循環を悪くさせて免疫力を低下させます。植物性の油を優先して摂りましょう。
植物性の油とはオリーブ・オイル、ごま油、大豆油などがあります。
米ぬか多糖体を白湯と合わせて飲めば、転移予防に効果があるでしょう。
膵臓をリラックスさせ、 腸管へ熱が伝わり自律神経が活性します。


医療法人健身会
周東寛 理事長
免疫力アップさせる成分
RBS米ぬか多糖体の
期待できる効果・効能