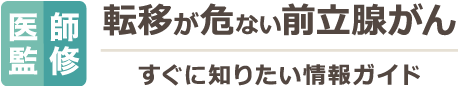骨転移を遅らせる治療法
このページの監修医師
医療法人健身会
周東寛 理事長
前立腺の骨転移に対する治療方法について、くわしく紹介しているページです。
骨関連事象の管理が予後の改善に繋がる
骨はがんが転移しやすい部位のひとつ。骨転移は悪性腫瘍のおよそ半分に起きると言われており、その中でも、前立腺がんは乳がん、肺がんと並んで骨転移しやすいがんなのです。
骨転移は、それ自体が命に関わることはありませんが、骨折や麻痺などを引き起こし、治療中のQOLを低下させる原因になってしまいます。
こういった場合、以前は痛み止めの処方をはじめとする緩和ケアが行われることが多かったのですが、近年では「骨関連事象」が起きるのを遅らせる治療が積極的に行われています。
「骨関連事象(通称SRE:skeletal related event)」というのは、骨の病変進行に伴って生じる痛み、骨折、麻痺、脊髄圧迫、外科的手術などの総称。
杏林大学付属病院泌尿器科准教授・桶川隆嗣氏によると、骨関連事象の管理をしっかりと管理した場合、管理しなかった患者よりも予後が良いそうです。
骨細胞とがん細胞が協力して病気を進行させる
骨折や麻痺が起きれば、痛みをはじめとする身体的な苦痛が生じるのはもちろん、生活する上での困難も増えます。その結果、寝たきりになってしまうと体調の悪化が免れません。長期間にわたる寝たきり生活は体力を低下させ、様々な健康上の弊害を生じさせる原因になってしまうのです。
しかし、骨関連事象ががんに与える影響はそれだけではありません。がんが転移した骨細胞は、がん細胞と協力して病気を進行させてしまいます。そのメカニズムというのは、以下の通り。
がん細胞は骨を破壊する働きを持つ「破骨細胞」という細胞の力で、骨に住み着くスペースを確保します。骨が破壊されると、そこに含まれていた細胞増殖因子が放出。この物質にはがん細胞の働きを高めてしまう働きがあるため、破骨細胞も活発に働くようになり、病巣がさらに拡大してしまう、という訳です。
骨関連事象を遅らせる治療とは?
前立腺がんの骨転移に対する治療は、大きく分けて3種類、「がんに対する治療」「骨転移の進行を抑える治療」「骨転移によって生じる骨関連事象を改善する治療」です。
その中でも、骨関連事象を改善する治療はもっとも優先されるもの。たとえば、神経圧迫によって麻痺が生じた場合、一刻も早くその状態を解消しなければなりません。なぜなら、神経細胞は一度死んでしまったら再生できないからです。脊椎の圧迫を取り除くために外科手術を行ったり、精巣摘出によって男性ホルモンの働きを低下させ、病巣に放射線をかけたりする治療が行われることもあります。
骨転移に対する一般的な治療薬
骨転移の進行を抑える治療薬として多く使われている、ビスホスホネート製剤のゾメタ(ゾレドロン酸水和物)という薬があります。これは元々高カルシウム血症や骨粗しょう症の治療薬として認可されたものですが、近年では前立腺がんの治療にも用いられるようになってきました。
ゾメタは骨の中に取り込まれ、破骨細胞の働きを妨害する働きをします。前述のとおり、がん細胞は破壊された骨から放出される細胞増殖因子によって増殖するので、骨の破壊を食い止めることによって、腫瘍の増殖を抑制する効果が期待できるという仕組みです。
ゾメタの効果に関しては
人における治験はまだありませんが、タキソテールと併用すると、がん細胞がアポトーシス(細胞死)を興す割合が3倍になるとの報告もあります。私たちの病院でも併用で治療を行いますが、中にはがんが消えた症例もあります。
引用元:がんサポート2012年9月号 桶川隆嗣『骨転移を遅らせる治療にはがんの進行を抑える効果も!』
という専門医の意見もあり、実際にがんの改善が確認されています。
そしてもうひとつ、骨転移に効果的な治療薬として保険適用で使われるようになったランマーク(デノスマブ)という薬。こちらは、骨芽細胞が破骨細胞に送る、分化を促すシグナル(RANKL)を妨害するという働きをします。
ゾメタとランマークの比較試験も行われましたが、ランマークを使用した患者たちはゾメタを使用した患者たちよりも骨関連事象の発生が8.2カ月も遅かったという結果が出ています。しかも、そのゾメタでさえ、何の薬も投与しなかった患者に比べて骨関連事象の発生を5.6カ月遅らせることができたという臨床試験結果もあります。
続々登場する期待の新薬
広く使われているゾメタやランマークに続いて、骨転移治療に対する効果が期待される薬が新たに登場しています。放射性医薬品である「塩化ラジウム-223」がそのひとつ。
塩化ラジウム-223の特徴は、骨代謝の活発な部分に取り込まれ、骨転移巣を標的とする放射線の一種であるα線を放出することです。α線は高いエネルギーを持ち、高い頻度で腫瘍細胞の構造を破壊し、そのDNAの複製を妨害する働きをします。
また、従来の放射性医薬品よりも高い効果を発揮しつつ、副作用が少ないという点も見逃せないメリット。前述のα線は放射範囲が100μmと狭いため、正常な組織や骨髄に対する影響も比較的少ないそうです。
骨転移を有する去勢抵抗性患者を対象にして行った臨床試験では全生存期間(病状は問わず、何年生存したかという尺度)の延長が確認されており、プラセボ患者の全生存期間11.3カ月(中央値)に対し、ラジウム-223投与患者の生存期間は14.9カ月(中央値)というデータが報告されています。この薬に対し、東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科教授・鈴木啓悦氏は骨転移にフォーカスした薬で、初めて全生存期間を改善しました。ゾメタやランマーク、同じタイプの放射性医薬品であるメタストロンも骨関連事象は改善しましたが、全生存期間は改善していませんでしたから、画期的なことです。
引用元:がんサポート2016年1月号 鈴木啓悦『骨転移と併せて骨粗しょう症対策が重要。前立腺がんの骨転移治療』
と述べています。がん治療において最も重視される尺度である全生存期間を改善したというラジウム-223は、まさに期待の新薬と呼ぶにふさわしいのかもしれません。
骨転移治療前の口腔ケア
鈴木啓悦氏は、骨転移の治療開始前には、まず歯科を受診する事が重要だと述べています。
前述の通り、骨転移を食い止め、前立腺がん患者の治療にも用いられているゾメタ、ランマークという薬ですが、その副作用として顎骨壊死(がっこつえし)を起こす可能性があるのです。顎骨壊死というのは、顎の骨が腐って壊死してしまう症状のこと。上記治療薬の投与中に抜歯などを行うと顎骨壊死が起きるリスクが高くなってしまうのですが、口の中をきちんとケアしておくことで、そのリスクを抑えることが可能なのです。
さらに、鈴木啓悦氏は薬の投与を開始してからも定期的に歯科を受診し、プラークコントロールなどのメンテナンスを行う事を推奨。骨転移治療以外でも、将来的にタキソテール(抗がん剤)などを使った化学療法を行うのであれば、事前に口腔ケアを行っておく必要があるのだそうです。
骨転移に伴う痛みには薬以外の選択肢も
ここまで、骨転移に対する治療方法として治療薬を中心に説明してきましたが、骨転移の痛みに対しては、薬以外の方法を選んだ方が利点が大きい場合もあります。
骨転移に対する放射線治療は鎮痛薬による薬物療法とは違い、がんによる痛みへの原因療法。そのため、骨転移痛のある患者の場合は放射線治療、もしくは放射線治療と他の治療法の併用によって、痛みの緩和や完全消失が得られるのが普通です。
ただし、骨転移に対する放射線治療は、麻痺リスクが迫っている時や痛みの激しい時など、限られた条件でしか行われません。放射線治療にも合併症などのリスクが存在し、放射線量の上限が定められています。そのため、放射線を当てる回数や一度に当てる量などについては慎重な判断が求められるのです。
もちろん薬に関しても同じことが言えますが、それぞれの治療法の性質と患者のコンディションを考慮し、適切な方法を選択することが重要だと言えますね。
早期発見の重要性
がん治療そのものにも同じことが言えますが、骨関連事象によってQOLの低下を招かないためにも、骨転移を早期に発見し、対処していくことが重要です。
骨転移の発生を確認するためには画像検査が必要ですが、より早期発見を望むのであれば、血液検査の数値を確認していく必要があります。
横浜市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学准教授・上村博司氏によれば
「PSA(前立腺特異抗原)の値が上昇するのはもちろん、ALP(アルカリホスファターゼ)の値が上がってきたら、ちょっとあやしいなという段階です。その場合、もっとくわしく調べるために、骨代謝マーカーの検査を行います」
引用元:がんサポート2012年9月号 上村博司『前立腺がんの骨転移は「早期発見・早期治療」が肝心』
とのこと。
骨代謝マーカーには、骨型アルカリホスファターゼ、I型コラーゲンC-テロペプチド、I型コラーゲン架橋N-テロペプチド、I型コラーゲンC-プロペプチドなどの種類があり、血液検査や尿検査によって骨転移の可能性を調査することができるのです。
骨代謝マーカーの数値が上昇してきたら画像検査を実施。画像検査には単純エックス線検査、骨シンチグラフィ、CT、MRI、PET-CTなどの種類があります。
骨代謝マーカー
骨代謝マーカーは, 一般的に骨形成性のマーカーと骨吸収性のマーカーに分類される. 主な骨形成性のマーカーとしては, 骨型アルカリフォスファターゼ(bone specific alkaline phosphatase:BAP), オステオカルシン, I型こらーげnNプロペプチド(procollagen type I N-terminal propeptide:PINP), I型コラーゲンCプロペプチド(procollagen type I C-terminal propeptide:PICP)などがあり, 一方, 骨吸収性マーカーとしては, I型コラーゲン架橋Nテロペプチド(type I collagen cross-ilnked N-telopeptide:NTx), I型コラーゲン架橋Cテロペプチド(type I collagen cross-ilnked C-telopeptide:CTx), I型コラーゲン末端テロペプチド(carboxyterminal telopeptide of type I collagen:lCTP), デオキシピリジノリン(deoxypyridinoline:DPD), ピリジノリン(pyridinoline:PYD), 酒石酸抵抗性フォスファターゼ(tartrate-resistant acid phosphatase-5b:TRAPC5b)などがある. がんの骨転移では, 骨代謝マーカーが高値を示すことがあり, ビスフォスフォネートや抗RANKL抗体などのBMAでは骨吸収を抑制することから, これらのマーカー値が低下することが知られている.
画像診断
骨転移の画像診断にはX線, computed tomography(CT), magnetic resonance imaging(MRI)、骨シンチグラフィー, fluorodeoxyglucose-positron emission tomography(FDG-PET)/CTが用いられる. どの検査も万全ではないため, 複数のモダリティーを併用して診断が行われる.
痛みのないうちから治療を開始する
早い段階で骨転移を発見することができれば、効果的な治療を行うことができます。ゾメタなどの治療薬を投与することによって骨が強化され、骨折などの骨関連事象を未然に防ぐことに繋がるのです。
しかも、痛みのないうちから投与を開始した方が、痛みが表れてから投与を開始するよりも骨関連事象を多く抑えられるという臨床データもあります。骨関連事象を防ぐことはQOLの向上や予後の延長に繋がるため、早い段階から骨の健康管理に気を配っていくべきです。
また、健康な骨の維持には、適度な運動を取り入れたり、骨に良い食生活を心掛けたりすることも欠かせません。ゆっくり散歩をしたり、カルシウムの豊富な乳製品、大豆製品を摂するように意識したり、無理のない範囲で生活を見直していくのが良いでしょう。
参照元:がんサポート2012年5月号 桶川隆嗣『骨転移を遅らせる治療にはがんの進行を遅らせる効果も!』
参照元:がんサポート2016年1月号 鈴木啓悦『骨転移と併せて骨粗しょう症対策が重要。前立腺がんの骨転移治療』
参照元:がんサポート2012年9月号 上村博司『前立腺がんの骨転移は「早期発見・早期治療」が肝心』
参照元:日本放射線腫瘍学会:放射線治療計画ガイドライン2012
骨転移治療の名医がいる病院
杏林大学付属病院

http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/
| 院長 | 市村 正一 |
|---|---|
| 住所 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
| TEL | 0422-47-5511 |
| 診療時間 | 平日 8:45-12:00、土曜 8:45-11:00 |
| 休診日 | 日曜、祝日、年末年始・学園創立日(11月11日) |
東邦大学医療センター
佐倉病院 泌尿器科

https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/sakura/urology/index.html
| 院長 | 長尾 建樹 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県佐倉市下志津564-1 |
| TEL | 043-462-8811(代表) |
| 診療時間 | 初診・再診 8:30~11:30、専門外来 13:00~16:00(再診のみ・予約制) |
| 休診日 | 第3土曜日、日曜日、祝日、年末年始 (12月29日から1月3日)、創立記念日 (6月10日) |
横浜市立大学附属市民総合医療センター

https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
| 院長 | 後藤 隆久 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目57番地 |
| TEL | 045-261-5656(代表) |
| 診療時間 | 9:00~16:00 |
| 休診日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 |
前立腺がん骨転移の予後に関する体験談
体全体のどこにも自覚症状は一切ありません
K・Fさん(男性)
2013年8月に通常の健康診断にて60歳にして初のPSA検査を受け、高値発見。
江戸川区の総合病院を紹介され、約3週間の総合検査結果は、(1)PSA値703、(2)生検結果12ヶ所の内8ヶ所、(3)グリソンスコア(悪性度)4+4=8、(4)股関節に骨転移1ヶ所(約5センチ)で、診断結果は前立腺がんD2でした。
医師からは手術/放射線治療等は不可能で無治療の場合余命2年および全身の骨転移で体が痛みだしたら余命1ヶ月との強烈な宣告を受け、本日よりホルモン療法を始めるという流れとなりました。
検査結果については予想外だったことと、家系的にはがん系統ではなかったので、がんについてはほとんどノーガードでした。
10日間位は、頭の中が真っ白になり、子どもや孫たちに何か言い残したことはないか等、余計なことが頭の中をかけ巡りましたが、人生の残された時間があまりないため、早速前立腺がんに関する情報等を専門誌/新聞や雑誌/インターネット等を読みあさり、複数の友人の医師にも情報を聞きまくり、今後の方針として出した結論としては、三大医療を極力無視して現在のホルモン療法(20%対処療法)を続けながら80%の代替療法で限りなく自己免疫を上げて戦うしか方法はないと判断しました。
現在、(イ)ホルモン剤ゴナックス(4週に一度腹部注射)、(ロ)骨転移防止剤ゾメタ(4週に一度点滴)、(ハ)抗アンドロゲン剤プロスタール(1日1錠)を使っています。
過去において、抗アンドロゲン剤カソデックスを3ヶ月服用で肝臓の数値700まで上がり中止。
その後オダインを2週間服用しましたがホットフラッシュと心臓の動悸が激しく中止。
そして現在のプロスタールで落ち着いています。
股関節の骨転移部分は4~5センチと比較的大きいため将来骨折の恐れがあるとのことで、2014年1月に10日間IMRT(トモセラピー)放射線治療(32グレイ)を行い、同年4月の検査結果で同部分の転移は完全消失。
治療前から現在に至るまで、体全体のどこにも自覚症状は一切ありません。
カテーテルを装着したまま5日間働き続けました
須田為義さん(男性)
2005年4月13日のことでした。
尿意があっても排泄ができないのです。
すぐ病院へ行き、カテーテルを通して出しました。
500㏄は溜まっていました。
それは鮮血も無くきれいなおしっこでした。
病名を告げられたのは翌日です。
『前立腺がんの末期』ということでした。
そして、『骨盤に転移してるので手の施しようがない。
2か月の命』とまで言われたのです。
確かに腫瘍マーカーPSA値は41.8(正常値3以下)と高く、MRIの画像では右骨盤の半分にがんが広がってるのが分かりました。
先生からは、治せないけれど延命のためといったところでしょうか。
『ただちに入院して放射線治療をしていきましょう』との提案がありました。
実は、余命宣告にショックを受けることはありませんでした。
私は、ぶどう農園を営んでいます。
4月からその年の手入れを開始したばかりで、頭の中はぶどうのことでいっぱい。
自分のことを考える余地など無かったのです。
そこで『入院するのはぶどうの収穫が終わる10月まで待ってください』と申し出ました。
すると先生は黙り込んでしまわれて。
『もう勝手にせい』ということだったのでしょうね。
その後、カテーテルを装着したまま、農園で5日間働き続けました。
外してみてさらに5日間過ごしました。
でも再び排泄が出来なくなり、カテーテルのお世話にならざるを得ませんでした。
その際、自分なりに考えてデポカボチャの種を7日間食べることにしました。
1か月分の目安量を1週間で食べました。
7日目にカテーテルを外してから自然排泄が出来るようになり、その後カテーテルを必要とすることは二度と無くなりました。
免疫力アップさせる成分
RBS米ぬか多糖体の
期待できる効果・効能